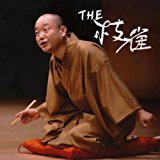
緊張の緩和理論
快感というものが、つまり人間がええ塩梅と思うことがいわゆる緊張の緩和なんですよね。それの現れが「笑い」ということなんですね。
全ての笑わし方の根底は、「緊張の緩和」なんです。
お笑いのすべては「笑いの分類」と「サゲの分類」に当てはまる
お芝居の喜劇であれ、映画であれ、コメディであれ、漫画であれ、全てが例えば「サゲの4種類」なんかに限って言えば、もちろん緊張の緩和で笑いが起こる。それに「知的なもの」「情的なもの」「生理的なもの」「社会的なもの」全てが当てはまる。
笑いの分類
①知的な笑い「変」
知的という言葉に間違って引っかかってもらったら困るんですが。頭を使った変なことという意味です。つまり正常でないこと、頭で考えて正常でないこと。人間、普通なことが安心、つまり緩和なことであって、変なことは緊張ですわな。でこれは、オカシイということが可笑しいということになりますでしょ?同じ言葉としても。オカシイと可笑しいが一緒でしょ?それを表してる。
いわゆる変が緊張なんです。
②情的な笑い「他人のちょっとした困り」
これは「困り」ということが緊張の1つの表現なんですよ。情的に言うと困ってることが緊張なんですよ。自分が困るということが緊張なんですよ。困らないということが緩和なんですよ。
困り過ぎると緊張が過ぎてしまって笑いごとではなくなる。だからちょっとした困り、緊張という言葉になる。
③生理的な笑い「緊張の緩和」
実はこの生理的なものが全体をくくっていることになっています。
純粋な生理的なものっていうのはね。例えば、赤ちゃんの「いないいないばぁ」。
「ばぁ」のところで始めは笑わないがきっかけがつけば笑う。赤ちゃんとしては始めは緊張が勝ちすぎているから笑わない。他人がやっても笑わないが、お母さんが言ったら笑う。「ばあ」というのが緊張なわけです。
赤ちゃんとしては、緩和が土台にあるから笑う。緩和の土壌のあるとこでちょいと緊張を与える。これが生理的な緊張の緩和。
④社会的な笑い・道徳的な笑い「他人の忌み嫌うこと」
これも緊張ですわな。ここで言うたらいかんことはこんだけあんでということですね。それも過ぎてしまうととても笑ってられない。なにを言うんだとなってしまいますから、ちょいとしたことですね。ちょいとシモがかったことに軽く触れるとか、これも緊張ですわな。言ってはいけないという緊張。
サゲの分類
1,ドンデン「合わせ→離れ」
物語が合いそうになってから離れる。
物事がうまく収まる(安心な方向に進む)と見せかけて、最後は覆される展開(どんでん返し)で終了する。
「そんなアホな…」とツッコミが入るオチ。(落語の例)愛宕山
2,謎解き「離れ→合わせ」
物語が離れそうになってから合う。
物事が予想もしない(不安な方向に進む)展開になるが、最後は納得の結末(謎が解ける)で終了する。
「なーるほど…」とツッコミが入るオチ。(落語の例)皿屋敷
3,へん「離れ(不安ウソ)」
突然に「変さ」(不安な結末)が訪れる。
「そんなアホな…」とツッコミが入るオチ。(落語の例)池田の猪飼い
4,合わせ「合わせ(安心ウソ)」
上手いこと「合わせ」(安心な結末)にいく。
「なーるほど…」とツッコミが入るオチ。(落語の例)蔵丁稚
古典的な分類
落語の落ちとしては最も一般的な分類法だが、分類の視点が統一されていないなどの欠点がある。
-
地口落ち
- 駄洒落の落ち、「にわか落ち」とも。「転失気」「錦の袈裟」が代表例。
-
拍子落ち
- 調子よく話が進んで終わるもの。「山号寺号」が代表例。
-
逆さ落ち
- 立場が入れ替わるもの。「一眼国」「初天神」が代表例。
-
考え落ち
- パッと聞いたところではよく分からないがその後よく考えると笑えてくるもの。「野ざらし」「疝気の虫」が代表例。
-
まわり落ち
- 結末が、噺の最初に戻るもの。「のっぺらぼう」が代表例。
-
見立て落ち
- 意表をつく結末になるもの。「もう半分」が代表例。
-
間抜け落ち
- 間抜けなことを言って終わるもの。「時そば」が代表例。
-
とたん落ち
- 決めの台詞で終わるもの。「厩火事」「弥次郎」が代表例。
-
ぶっつけ落ち
- 全く関係のないことで終わりにする。「やかん」が代表例。
-
しぐさ落ち
- 身振りで表して終わるもの。話芸による落語のなかでも特異であると言える。演者が実際に高座で倒れる「死神」が代表例。
-
冗談落ち
- 本来の下げまで語ると持ち時間内で収まらないとき、切りの良い所で「冗談言っちゃいけねえ」と終わらせる。


